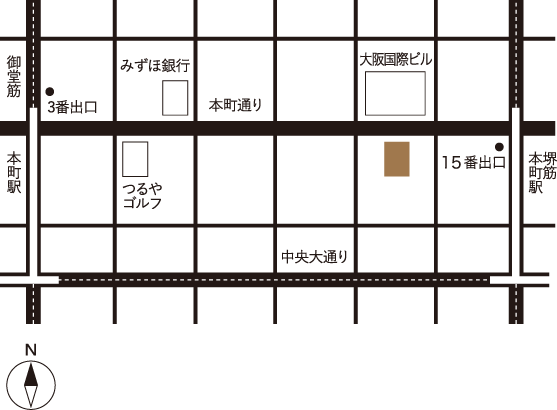解雇無効で発生するバックペイと使用者の対応・反論

1 はじめに~バックペイのリスクと使用者の判断
懲戒解雇であれ普通解雇であれ、解雇時点においては、解雇が有効であるというのは法的に確定されていないという意味では使用者側の主張に過ぎません。
解雇された労働者は、解雇に納得が出来ない場合、当該会社の従業員の地位にあることを確認する訴えを提起し、その中で解雇無効を主張してきます。
そして、その後判決によって当該解雇が無効であることが確定した場合、使用者は従業員が就労意思がありながら就労出来なかった間の賃金を遡って支払う義務が生じます。これがいわゆるバックペイと言われるものです。
通常、訴訟提起がされてから上告審での判決確定まで、2年程度を要することは多々あります。その場合、単純に計算しただけでも、仮に給与額が30万円の従業員に対しては、30万×24月=720万円のバックパイと法定利率の遅延損害金を支払わなければなりません。
使用者としては、このようなバックペイのリスクを想定しながら解雇の判断をする必要があります。ケースバイケースではありますが、仮に問題社員であったとしても、話し合いでの退職の余地がある場合には、使用者としても一定の経済的補償をした上で、円満に合意退職をしてもらうことは上記したリスクを考えれば、結果として双方にとってメリットのある解決になり得ます。
2 バックペイの根拠
このようなバックペイが発生する法的根拠は民法にあります。
民法536条2項には、
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
という規定がありますが、これがバックペイの根拠になります。一見分かりにくいですが、これを次のように読み替えるとおわかりいただけるかと思います。
使用者の責めに帰すべき事由によって労務提供することができなくなったときは、使用者は賃金支払を拒むことができない。
3 中間収入(中間利益)の控除に関する使用者側の反論
もっとも、民法536条2項には続きがあり、
但し、この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
という規定があります。
これも分かりやすく言い換えると、
但し、この場合において、従業員は、労働提供を免れたことによって収入を得たときは、これを使用者に償還しなければならない。
と読み替えることが可能です。
解雇無効を争う労働者は、その間従来の収入を得ることが出来ないため、(一定期間、失業保険の仮給付を受けることも可能な方もいますが)アルバイトをしたり等で生活を行なう方もいます。
このような場合、従業員は使用者にバックペイの支払いを請求できる一方で、就労を拒絶されていた期間に現実に得た収入(中間収入)は、民法536条2項但書によって償還(控除)しなければなりません。法的には使用者側の反論として主張していくこととなります。
4 控除される中間収入の範囲
民法には、控除される中間収入の範囲について具体的規定はなく、判例上は、労働基準法26条の趣旨を勘案して次のように考えられています。
労働基準法26条は、「使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、休業期間中は少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」と定めています。これは、直接には使用者都合での休業手当に関する規定ですが、バックペイ算定の場合にも、この規定を用いています。
規定上もう1点確認が必要であるのは、「平均賃金」とは何かということです。これについては、労働基準法12条1項で「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」とされており、また、同条4項により「賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。」と定められています。
以上を踏まえ、次のような解釈が最高裁の判例上確立されています。
まず、解雇期間中に当該従業員が当該使用者から支払われるべきであった賃金のうち、平均賃金の6割を超える部分から、当該賃金支給の対象とされるべき期間と時期的に対応する期間内に当該従業員が他から得た中間収入の額をまず控除することが出来ます。
そして、中間収入の額が平均賃金の額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定基礎とならない賃金の全額から控除することが出来るとされています。
以上の判例法理により、解雇期間中の賃金が月額30万円、平均賃金も月額30万円であった場合、平均賃金の6割を超える部分から中間収入を控除することとなりますので、仮に中間収入の額が5万円であった場合には、30万円から5万円を控除した25万円が最終支払額となります。
一方、中間収入の額が仮に20万円であった場合には、これを全額控除した場合には平均賃金の6割を確保することが出来ません。
このような場合には、例えば、他社で賞与など平均賃金算定基礎から除外される収入を得ていた場合には、その全額から控除することができるとされているのです。
雇用の形態によって平均賃金の算定方法も異なり、また平均賃金算定基礎とならない手当等も種々であり、それが算定基礎に含まれるべきであるのか否かについての争いも生じる場合があります。
個別事例毎に判断すべき内容を多く含みますので、解雇判断と合わせてご相談、ご検討をいただきたいと思います。
谷川安德
最新記事 by 谷川安德 (全て見る)
- 退職代行と弁護士法違反について解説 - 2025年10月23日
- リベンジ退職社員?による従業員の引き抜きと損害賠償請求の可否 - 2025年10月8日
- 会社貸与PC等の私的利用について弁護士が解説 - 2025年8月1日
「解雇無効で発生するバックペイと使用者の対応・反論」の関連記事はこちら
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2026.01.13セミナー/講演
- 問題社員に対応できるモデル就業規則~実務で使えるモデルを構築する~ 2026.03.11
- 2025.12.25お知らせ
- 年末年始のお知らせ
- 2025.12.17セミナー/講演
- 【実施済】∼ 2026年施行 ∼ 企業法務に影響する 重要法改正 2026.02.18
- 2025.11.22お知らせ
- 弁護士谷川安德が企業向けハラスメント研修講師を担当致しました。
- 2025.10.23コラム
- 退職代行と弁護士法違反について解説