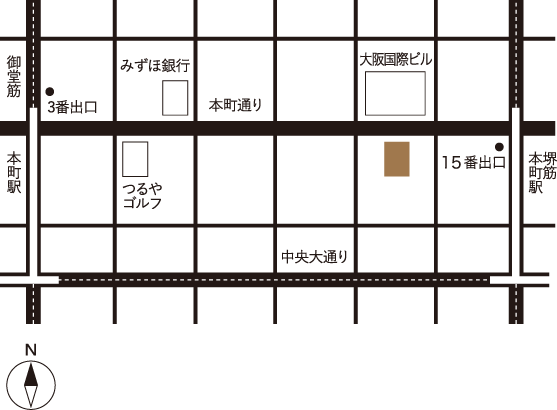就業規則の周知性~効力ゼロにならないために~

1 はじめに
就業規則については、「周知性」の要件が必要であることは比較的良く知られているかと思います。
もっとも、「周知性」の要件は、行政監督の対象となるという意味での「周知性」と、就業規則が対従業員との関係で効力を生じるための要件となるという意味での「周知性」とでは、必ずしも一致しません。
2 行政監督対象としての「周知性」
労基法106条は、その1項において
(法令等の周知義務)
第106条
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
と定め、労基法施行規則は、
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
と定めています。
これらの規定による周知性を欠いている使用者については、罰則付きで行政監督対象としています。
条文から明らかなように、就業規則の現実的な交付や、各作業場における備置閲覧を求めており、一定の様式性を求めていると言えますし、対象を限定的に列記しています。
3 効力要件としての「周知性」
一方、就業規則の契約内容効(労契法7条)や契約変更効 (10 条)の要件となる周知については,裁判上もこれとは異なり、必ずしも一定の様式を備えることまで求められていません。それは必ずしも要件を緩和するという意味ではありませんが、発想としては、「労働契約関係にある当事者(主には労働者)を就業規則の内容で拘束して良いか」という評価的な視点で検討するものであり、これら労基法の定める限定的・様式的な周知性と区別する意味で、「実質的な周知性」で足りるという説明がなされています。
この「実質的な周知性」は、様式的なものではなく、労働者が知ろうと思えば知りうる状態に置くことを指すと解されており、労働者が実際にその内容を知っているか否かは問われていません。したがって、上記状態に置いている限り、「見たことはなかった」という理由では、周知性は否定されてません。
例えば、東京地判平成18・ 1 ・25労判912号63 頁は、次のように判示しています。
まず、「実質的周知性」については、「就業規則が法的効力を有するためには、従業員代表の意見聴取、労基署への届出までは要せず、従業員に対し、実質的に周知の措置がとられていれば足りると解するのが相当である。なぜなら、使用者が義務を履践しないことにより就業規則の効力を免れるのは相当ではないからである。そして、ここにいうところの実質的な周知とは、従業員の大半が就業規則の内容を知り、又は知ることのできる状態に置かれていれば足りる解するのが相当である。」
とした上で、本件では、
・就業規則は事務用の書棚にファイルされて置いてあり、同支店の従業員であればいつでも閲覧できるようになっていた
・黒い背表紙のファイルに入れて支店の書棚に置いてあり、書棚には鍵はかかっていなかったため、同支店の従業員はいつでも見ることができた。また、同じファイルに遅刻、欠勤、有給休暇等の勤怠の申請用紙も入っており、被告千葉支店の従業員はそこから用紙をとっていたことから、当該ファイルの存在をよく知っており、ファイルに就業規則があることも十分に認識していた
・原告のうちAは、被告大阪支店の支店長であり、通常、就業規則の内容を知らないで従業員の管理をすることは困難
等(一部事実認定のみ抜粋しています。)等を認定し、実質的周知性を認めました。
このように、実質的周知性は、様式性を要しないという点では実質的で「足りる」という言い方も出来ますが、就業規則が労働者に対し、使用者の定める労働条件を拘束させるものである以上、特に、賃金制度を変更させるような場面においては、労働者に対する周知や、説明の誠実性、具体性などは実際の裁判例においては、使用者に厳しめに判断される可能性があるものとして、平時の管理が必要です。
4 実質的周知性が大前提であること
労使間の紛争において、就業規則を前提とする紛争はほとんどと言えます。
例えば、懲戒処分も就業規則に具体的に定めがない限り、これを行なうことが出来ません。
例えば、懲戒解雇を就業規則に基づき行なったとしても、実質的周知性が否定されれば、解
雇無効となります。
また、例えば、就業規則やこれに付随する賃金規定等において固定残業代の定めがあり、その定めが仮に固定残業代の有効性要件を備えていたとしても、実質的周知性が否定された場合には、支払済みの固定残業代分は、残業代の支払いとは認められません。
中小企業の多くにおいて、この実質的周知性は現場における見直しが一番最初に必要な要件の一つですので、今一度、ご確認をお願い致します。
谷川安德
最新記事 by 谷川安德 (全て見る)
- 退職代行と弁護士法違反について解説 - 2025年10月23日
- リベンジ退職社員?による従業員の引き抜きと損害賠償請求の可否 - 2025年10月8日
- 会社貸与PC等の私的利用について弁護士が解説 - 2025年8月1日
「就業規則の周知性~効力ゼロにならないために~」の関連記事はこちら
- 「事業場外みなし労働時間制」による反論
- 「働き方改革」とは何か
- 1年単位の変形労働時間制について弁護士が解説
- テレワーク導入と就業規則の関係
- フレックスタイムの導入について弁護士が解説
- 事業場みなし労働時間制と裁量労働制
- 令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります
- 企業が定める休職規定について
- 働き方改革で変わる割増賃金請求への対応策
- 労使協定の締結について
- 労働基準法における労働者とは何か?~フリーランスや劇団員等の事例はどのように考えるべきか~
- 労働時間と休憩に関する近時の裁判例について弁護士が解説
- 労働時間の管理
- 労働条件の不利益変更における労働者の「同意」の有無の判断
- 労働条件の不利益変更の実務~固定残業代の手当減額の可否と限界~
- 労働条件明示ルールの変更と「配転命令」の有効性~その1~
- 労働条件明示ルールの変更と配転命令 その2~配転命令をめぐる紛争~
- 同一労働同一賃金~不合理な待遇差の診断、対応プラン
- 同一労働同一賃金とは?制度の趣旨・概要や2021年度法改正に向けた対応内容について解説
- 同一労働同一賃金における賞与と退職金の取扱いの注意点
- 変形労働時間制
- 就業規則のリーガルチェック
- 就業規則の周知性~効力ゼロにならないために~
- 就業規則の実質的周知とは?企業が抑えるべきポイントと注意点
- 復職判断における「治癒」とは何か?について弁護士が解説
- 懲戒処分としての減給
- 新最高裁判例紹介~同一労働同一賃金
- 育児・介護休暇、休業
- 育児・介護休業法改正~令和4年以降の施行対応について~
- 育児介護休業法の改正対応について
- 裁量労働制を採用する使用者の反論
- 賃金の支払いについて
- 退職金不支給・減額条項に関するポイント解説
- 高度プロフェッショナル制度とは?制度の概要・要件・導入手続を弁護士が解説
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2026.03.10企業向けセミナー
- 敗訴事例から学ぶ敗けないための労務管理~裁判所は何を見ているのか~
- 2026.01.13セミナー/講演
- 問題社員に対応できるモデル就業規則~実務で使えるモデルを構築する~ 2026.03.11
- 2025.12.25お知らせ
- 年末年始のお知らせ
- 2025.12.17セミナー/講演
- 【実施済】∼ 2026年施行 ∼ 企業法務に影響する 重要法改正 2026.02.18
- 2025.11.22お知らせ
- 弁護士谷川安德が企業向けハラスメント研修講師を担当致しました。