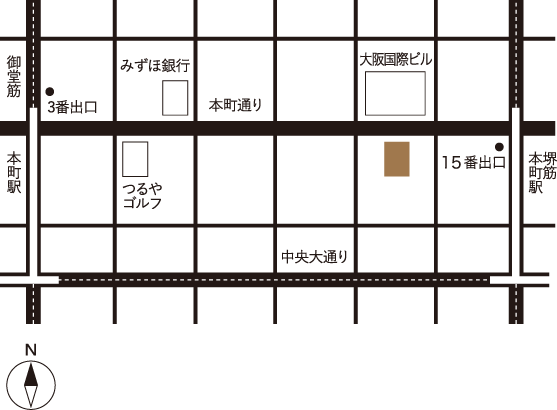労働条件の不利益変更の実務~固定残業代の手当減額の可否と限界~
Contents
1 はじめに
本稿では、固定残業代の手当減額を題材として、それが労働条件の不利益変更にあたるのか否か、その場合の就業規則の変更の限界点などについて概説致します。
2 そもそも「労働条件」とは?
就業規則の変更による労働条件の変更に関して、労働契約法第9条は「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない(以下略)」として、条項中に「労働条件」という文言を用いていますが、法律は「労働条件」とは何かについて特段の定義規定を置いていません。
「労働条件」という文言自体は、労働基準法第1項第1項で、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」として、使用されている文言で、ここの条項における「労働条件」の意義は、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿者等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇のことであると言われています。
他にも、憲法27条第2項では「勤務条件」という文言が使用されているほか、労働組合法等の他の法律においても「労働条件」という言葉が用いられ、就業規則の変更に関する上記労働契約法の「労働条件」の文言がこれらと同じであるかどうかは法令上は明らかではありません。
実務的には、これらを必ずしも統一的に定義するのではなく、それぞれの法令や条項の趣旨・目的に照らして検討する必要があります。よって、就業規則の変更の場面における「労働条件」としては、予防法務の視点としては、労働契約に際して明示が求められる労働条件の内容を中心に、労働契約及びこれに付随した契約に基づいて生じる労働者の職場における待遇に関しては一応「労働条件」と捉えたうえで、不利益変更該当性も一応想定したうえで、その合理性を慎重に検討することが必要と考えられます。
3 労働条件の不利益変更
労働契約法は、第9条において、
(第9条)
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
とし、次条である第10条本文において、
(第10条)
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
との規定を定めています。
下線部について、厚生労働省の通達によれば、それぞれ以下のように説明されています。
①労働者の受ける不利益の程度
実際に紛争となる事例は、就業規則の変更により個々の労働者に不利益が生じたことに起因するものであり、個々の労働者の不利益の程度をいうものであること。
②労働条件の変更の必要性
使用者にとっての就業規則による労働条件の変更の必要性をいうものであること。
③変更後の就業規則の内容の相当性
・就業規則の変更の内容全体の相当性をいうものであり、変更後の就業規則の内容面に係る 制度変更一般の状況が広く含まれるものであること。
・「代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況」、「同種事項に関する我が国社会における一般的状況」も含まれるものであること。
④労働組合等との交渉の状況
労働組合等事業場の労働者の意思を代表するものとの交渉の経緯、結果等をいうものであること。「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者のほか、少数労働組合や、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体等労働者の意思を代表するものが広く含まれるものであること。
⑤その他の就業規則の変更に係る事情
上記①~④を含め就業規則の変更に係る諸事情が総合的に考慮されることをいうものであること。
行政解釈と裁判所の判断は一致するものではありませんが、裁判所においても行政解釈は一つの参考として致しますので、不利益変更に関する合理性判断については、上記行政解釈は意識しておく必要がありますので、ここでご紹介致しました。
4 固定残業代の手当減額について
(1) 固定残業代の手当減額について検討
固定残業代についての詳細は別稿に委ねますが、固定残業代制度の有効性(残業代支払いとして認められるかどうか)については、日本ケミカル事件最高裁判例が、対価性(実際に時間外・休日・深夜労働に対する対価としての性格を有することが必要との要件)を必要とすることを明らかにしました。この対価性を充たすための制度構築にあたっては、何時間分のどういった手当の趣旨で支払っているのかを想定することとなりますが、例えば、50時間相当分の時間外労働の手当として、固定残業代名目で月額例えば20万円を支払っていた場合に、これを25時間相当分の時間外労働相当分に変更し、結果手当を10万円に減額することが労働条件の不利益変更にあたるのか、就業規則で変更した場合に合理性が認められるのか、が本稿での検討内容です。
まず、問題意識として、定額残業代については、仮に25時間分の時間外労働相当分の固定残業代の支払いを受けたとしても、実時間外労働時間が40時間であれば、その差額の精算は行なわなければなりません。
したがって、精算が行なわれる限り、当該労働者に支払われる額に変更が生じるわけではありません。
しかし、一方で、当該企業において実態として10時間相当分程度の時間外労働しか存しないような場合には、固定残業代の減額は、イコール月額給与の減額となりますので、この側面では不利益変更と捉えることが可能です。
よって、固定残業代の手当減額は、基本的には不利益変更にあたるとの前提にたって、合理性を検討すべきです。
(2) 脳・心臓疾患の認定基準との関係
脳・心臓疾患の労災認定に関しては、現在、令和3年9月14日付け基発0914第1号「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」で示された認定基準が、行政の労災認定基準となっています。
厚生労働省は、この基準策定にあたり、脳・心臓疾患の発症と睡眠時間、労働時間及び労働時間以外の負荷要因との関係について最新の医学的知見の収集を行うとともに、専門検討会を設定しました。そして、その専門検討会において、令和3年7月、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」がとりまとめられ、その中において、長期間の過重業務における労働時間の負荷要因の考え方としては、旧認定基準と同様に、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
② 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
を踏まえて判断することが妥当である
との報告がまとめられています。上記認定基準はこの専門検討会報告書を受けて策定されたものですが、脳・心臓疾患において「100時間」「80時間」といった時間数が過労死基準等と言われることがあるのも、こうした知見に基づいているものです。
(3) 時間外労働規制との関係
また、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、45時間・年360時間とされ、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできず、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要があります。
(4) 割増率との関係
もう一つ参考となる時間としては、時間外労働の割増賃金率について、中小企業について猶予されていた月60時間超の残業割増賃金率も2023年4月1日からは、大企業、中小企業ともに50%となります。
(5) 以上の考察からいえること
まず、少なくとも脳・心臓疾患との関連が強いとされる時間外労働については、労働者の健康、安全を図るためにも抑制されるべきであり、そもそも月80時間以上を前提とする固定残業代については、それ自体が公序良俗違反と判断される可能性が高いといえます(東京広汎平成30年10月4日労判1190号5ページ)。
よって、仮に月額80時間以上を想定しての固定残業代が設定されているのであれば、そもそも想定時間を抑制的にすべきであり、その変更を行なうこと自体はむしろ必要と考えられます。
では、何時間相当分までが合理性を有するかということですが、法律が時間外労働の上限を原則として月45時間としていることや、月60時間超の残業割増賃金率が50%以上とされていること(割増の趣旨は時間外労働を抑制する目的を有しています。)からすると、「45時間」「60時間」という数字は、固定残業代の制度設計において参考とすべき数値と言えます。
したがって、「45時間」「60時間」あたりを前提にする想定労働時間数の減少、それに伴う手当減額については、労働安全衛生上も相当に合理性を有する内容であり、変更の合理性は認められやすい内容になるものと考えます。
もっとも、真に労働安全衛生を考える上においては、実際に超過精算が生じないように、実際の時間外労働もこれら時間内に収めることが企業に求められる姿勢といえます。
5 最後に
固定残業代については、導入から設計後の変更まで、検討課題も多い内容を有するものです。しっかりとした想定、運用、労働者への説明が求められますので、事前に十分な検討を行なっていただきますようお願い致します。
谷川安德
最新記事 by 谷川安德 (全て見る)
- 改正公益通報者保護法が成立しました - 2025年6月30日
- ハラスメント窓口において参考とすべき事実認定の手法 - 2025年5月31日
- 時間単位の有給休暇、上限を「5日以内」から「全体の50%」に緩和…規制改革会議が中間答申へ - 2024年12月25日
「労働条件の不利益変更の実務~固定残業代の手当減額の可否と限界~」の関連記事はこちら
- 「事業場外みなし労働時間制」による反論
- 1年単位の変形労働時間制について弁護士が解説
- テレワーク導入と就業規則の関係
- フレックスタイムの導入について弁護士が解説
- 事業場みなし労働時間制と裁量労働制
- 令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります
- 企業が定める休職規定について
- 働き方改革で変わる割増賃金請求への対応策
- 労使協定の締結について
- 労働基準法における労働者とは何か?~フリーランスや劇団員等の事例はどのように考えるべきか~
- 労働時間の管理
- 労働条件の不利益変更における労働者の「同意」の有無の判断
- 労働条件の不利益変更の実務~固定残業代の手当減額の可否と限界~
- 労働条件明示ルールの変更と「配転命令」の有効性~その1~
- 労働条件明示ルールの変更と配転命令 その2~配転命令をめぐる紛争~
- 同一労働同一賃金~不合理な待遇差の診断、対応プラン
- 同一労働同一賃金とは?制度の趣旨・概要や2021年度法改正に向けた対応内容について解説
- 同一労働同一賃金における賞与と退職金の取扱いの注意点
- 変形労働時間制
- 就業規則のリーガルチェック
- 就業規則の周知性~効力ゼロにならないために~
- 就業規則の実質的周知とは?企業が抑えるべきポイントと注意点
- 復職判断における「治癒」とは何か?について弁護士が解説
- 懲戒処分としての減給
- 新最高裁判例紹介~同一労働同一賃金
- 育児・介護休暇、休業
- 育児・介護休業法改正~令和4年以降の施行対応について~
- 育児介護休業法の改正対応について
- 裁量労働制を採用する使用者の反論
- 賃金の支払いについて
- 退職金不支給・減額条項に関するポイント解説
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2025.06.30コラム
- 改正公益通報者保護法が成立しました
- 2025.06.27セミナー/講演
- 労務管理体制の不備による重大トラブル4選 20250828
- 2025.06.02コラム
- 公益通報者保護法による公益通報者の保護規定の改正について
- 2025.05.31コラム
- ハラスメント窓口において参考とすべき事実認定の手法